
カルロスサウラ監督が『カルメン』(1983)で日本でブレークしたのは1984年である。つづけて1981年作(日本公開は1985年)の『血の婚礼』、1985年の『恋は魔術師』とアントニオガデス三部作がヒットする。もちろんこれはアントニオガデスという不世出のダンサーひきいる舞踊団のバレエあってのものであるけれども、その素晴しさを充分に伝える映画であった。ところで、『血の婚礼』では序章でガデスが自身の来歴を語り、本編は通し稽古というかたちで描かれる。舞台ではなく、レッスン室。衣裳はつけずに練習着。しかし、それがフラメンコバレエの迫力を却って見せつけている。『カルメン』では舞台カルメンとそれをつくるガデス楽団の物語が平行する。虚構である物語カルメンと現実である舞踊団がいりみだれラストのシーンではカルメンの伍長ドンホセがカルメンを刺したのか、ガデス舞踊団のガデスが刺したのかわからない、そしてその全体は虚構である映画におさまるというまあ、古いといえば古い仕掛になっている。
『恋は魔術師』では一転して、舞台装置のなか完全な衣裳で展開する。映画的なセットであり、劇映画ふうのつくりで、しかし、舞踏はガデス劇団のそれである。
しかし『フラメンコ』(1995)や『セビージャーナス』(1993)では『血の婚礼』(1981)や『カルメン』(1983)のときにはあったドキュメンタリー的あるいは劇映画的な作為を一切排除。アーティストの芸を将来の子孫とアーティストが公演に回れない地方の人に見せられるようにと記録映画に徹することで逆に劇映画のもつ安っぽさを回避して一分のスキもない完璧な映像を作っている。

舞台にはアンダルシアの廃駅が使用され、衝立でつくった舞台空間で歌手は歌い、奏者は奏で、舞踊家が舞う。照明はこの舞台のために特設されたという。美術はベルトルッチである。

カメラワーク、アップや視点の移動は劇映画的手法ではストーリーの展開に必須でも優れたアーティストの記録としてみたときには視聴者のさまざまな視線移動を不可能にして、特定の視線移動を強要する。よってこれを減じて、遠景を多用した視点をとることで10回見れば10回新しい発見がある映像となっている。とはいえ、それなりにアップや移動もあり完全に客席に固定というわけにはいっていない。映像という点では舞台美術の一貫としての演出がなされてはいる。
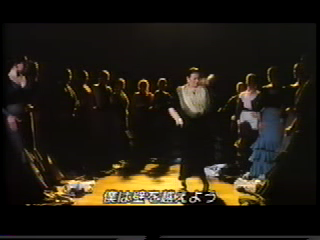
それでも、ここらへんアップの多用やまとわりつくようなカメラワークで舞台芸術を壊してしまう劇場中継とは一線を画してストイックな画像である。映画人としてはダンサーに完全に降伏することで逆に完全な映画ができるという皮肉である。しかし、こうなるとなぜ映画なのかという疑問があろうか。すでに舞踏で完全ならば、それをなぜ映画にするのかという疑問である。
わたしはアントニオガデスの舞台をただ一度だけ大阪で見ることができた。1995年である。前々年に引退を宣言するもこの公演の新作のため現役復帰したアントニオガデスはすでに55歳になっていた。風格と舞踏の表情にはさすがのものがあったけれども、スピードと切れにおいては若手に譲っていたのだった。結局日本に住むわたしは舞台では生涯に一度最晩年のガデスを見たきりである。そのガデスの、カルメンアマージャのあるいはクリスティーネオヨスの炎のような舞踏を見ることができるのはサウラの映画だけなのである。他のフラメンコ映画が劇映画調のつくりしかできなかったために肝腎のダンサーの舞踏が断片になってしまっているのとはまるで違う。必要最小限の加工しかしないといういわば刺身のような映画がそれゆえに劇映画を凌駕してしまっているのである。
ようするにサウラ監督は自身がフラメンコファンであり、これを見せたいのである。最高のアーティストの最高の芸を後世や海外のひとに。そして同時によい素材を扱う記録映画が作為的な劇映画よりはるかにまさっていることを示している。
2004/1/1